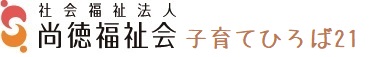第5回講演会 子どもが育つみちすじ⑨
子どもの時間というのはね、もしかしますと、みなさんも10歳頃までの出会った人たち、たぶん100人か1000人かそこいらでしょう。親しく出会った 人、この世に60億の人がいますけど、60億の人にいきなり会う訳じゃありません。100人か1000人の人に出会い、人ってこうなんだ。人の表情ってこ んな表情なんだ。怒る時こんなんだ、褒めるときこんな顔して褒めてくれるんだ。こういうのげんけい(原型)アーキタイプ基本系といいますが、人間というも ののイメージの現象、基になる形、イメージが入ります。
それを持って船出をする。いよいよ男の子、女の子が男、女になります。
背がある時自分を通過して行く。
みなさんもご経験ありますか?私も子どもがある時、私もかなり大きい方ですが、私を通過していきました。そして10代に入り、今までとは打って変わってややこしい子になっていきました。
ああ、思春期到来だなぁと思います。節目の川、性という節目の川渡っていきます。
えーそうすると動物ならもう親離れ子離れをしていいのに、人間だけは親離れ子離れがまだ先に、少し時間的に先送りされますね。ややこしいに決まってますよ。
家の中にね、成熟したオスとメスがいる訳でしょう。本当に子どもの部屋に入ると何とも言えない10代の子の部屋って生臭くてね、怪しげな物がいっぱいあっ てね、ちょっと開けてみようか、という誘惑もあったりして、見ようもんなら、もうそれこそどんなにやられるかわからないと思いながらも、ちらっと見てみた りなんかして。でもなんか悪い、絶対これは見たとは言うまいぞ、と思ってみたり。
喧嘩の途上でついポロッと言って、それこそ一ヶ月ほどものを言ってもらえなかったり、親ってやるもんです。で、怒る時にね、もう権威がなくなってますから、何を言っても“言いたかったら言ったら”っていう顔して聞いてますから。
もう年に2回ほど、どうしても言う時は、みなさんもやって下さい。私はたいてい椅子の上に上がって、ここから言うと、どうも見上げて言うのは権威がないん でね。これだけはここから言わせてもらうからね、って言うと、平然として「言いたかったら言ったら」っていつも言ってました。かつての、今やもう30女で すが、懐かしいです。
でねぇー思春期はね、危ないものと心得て下さい。あの、危ない方が、危ない方がっていうのは変ですが、危なくって健康なんです。素知らぬ顔して、あとで過ぎ去ったあと思い返せば、危なかったと思うのが大方のいわゆるよい子でいらっしゃる皆さんでしょう。
でも、危なかったってどこかで思われませんか。友だちについ誘われて行きそうになって、ギリギリで行かなかったとかな。あるいはギリギリで行っちゃって、 警察行ったことが一回あるとかね。たいした差じゃありませんよ。行ったか行かないかぐらいは、ちょっと向こうに行ったか行かないで、行った子は逆です。一 回でも行った子は、もう一生涯覚えてますからね、「いい経験したね」って私はよく非行の子に言います。
「もうあれ嫌だったでしょう、楽しいのならともかく嫌だったでしょう」
やっぱりね、危険って赤い字で書いてあって、ここはここ過ぎたら危険だって言われてて、そういうの書いてあったら不思議にそこへ行きたいもんなんです。10代ってね。
「でも、行ってみたら分かったでしょう、転んでもただで起きちゃ駄目だよ、大人になってね危険って書いてある、つまり法律っていうもの違反すると、もうそのギリギリで船を引き返しなさい。そこを越えたら見つかろうと見つかるまいと、必ず何かが待ってるからね」って。
「それをあなたは経験した。しなかったよりした方が良かったね。いい経験したねェ」ってよく非行児に言います。転んでもただで起きるなと言いたい。
それが自分のものになると、本当に一生涯生きていく時にプラスになります。法律違反ということがどんなに重いか、いい経験をしますからね。そういうのしな くて50代ぐらいになってね、政治家やら何やらが手痛い目にあったりするのを見ると、知っといた方が良かったんじゃないかと思ってさしあげたりして、自分 も割合上手に生きて警察に行ったことがないので、どこかひ弱でね。私も初めて捕まる時はきっと怯えきるだろうな、いつも怯えてますけども。
だからそれぐらいなら、まああっち側へ行かないように、なるべくしようと思うのですが、非行児に会うとややね、やや尊敬もこめて「あなた、先輩ね」って言いたくて、「いい経験だよ」って本当に言ってあげたくてね。
学校に行かない子や引きこもっている子も、人とつながるってなんて難しいだろうって思う。昨日まで口笛吹いてね校門入ってた訳ですから。それが何故にか校 門をくぐれなくなる、それは人間が駄目になったんじゃなくて、自分の中で自分の問題がおこってきている訳です。いいチャンスですよ。真っ直ぐ学校へ行って る子が立派でもなんでもない。たまたま人の背中見てね、運動会の行進みたいで、前の子が歩いてく後ろついて行けばどこかに行きますからね。
円をえがきましょうって言ったって、タッタタッタ行ってるだけで、自分一人で歩くったら大変ですよね。背中が前の背中がないんですもん。よくよく考えてみ たら、学校へ行ってたというのは別に「本当に行くぞ」って、毎日いちいち決心して行った訳でもなんでもなくて、ただ惰性で行っとったような気がしますか ら。
行かない子がね、ある時ちょっと靴紐直したり、ちょっとまわり見回してちょっと気持ちが重くって行かれなくなって、一日二日行かれなくなって、いわゆる不登校になるっていうのは、別に人間としてどこも失格ではなくいいチャンスだと思います。
それは、彼は立派とか立派じゃないじゃなくて、自分は何をしているんだろう、なぜ学校へ行くんだろうって、今まで考えたこともなかったでしょう。今考え る、あそこに人がいる、今まで友だちにあんまり悩んだことがなかったのに、たった一人の誰かのまなざしや声が気になって行かれない、あなたはそれだけ敏感 に世界を感じ始めたのねって言ってあげたいし、世界ってそう言うものよって。
そういう時が大人になってもいつの時代でもある。で、それを越えていく時に人と人とつながることが、前よりももっと深くなる。いいチャンスだから、また転んでもただで起きるなといつも言うんですが、何をやっても転んでもただで起きちゃ駄目よって、いい経験なんだから。
思春期はそういうことが言えて、私は思春期を一生涯の仕事にしたかったのは、いい季節だからです。だって真っ当な季節ですもの。10代をかけてしっかり悩 …