5歳ひまわり組2021年度3月の保育日誌
3月 2日(水) 曇り 萩原
ひな飾り作りで、昨日までに形作り・絵付けをしたものを装飾していく。図鑑や本物の雛人形を観察し、どんな装飾品を作りたいか考え、イメージを固めていく。ぼんぼり作りでは、トイレットペーパー芯を使って球体の枠組みを作り、立体的に仕上げていく児や、平面に作ってから、ちょうちんらしく見えるように形を変えていく児と、素材の選び方や使い方に工夫が見られる。また、図鑑を何度も確認して本物のように作ろうと試行錯誤したり、友達同士でアドバイスし合ったりする姿が見られる。出来上がると、自分が工夫したポイントや頑張ったところを話し合っている。中には、自分がイメージした通りに形作ることが難しく、困惑する児もいるが、どうにか自分の思うように作ろうとする姿に成長を感じる。クラス全体で、自分の作品をアピールする機会をもち、認め合ったり褒め合ったりすることでさらに自信を大きくできるように援助する。
3月 11日(金) 晴れ 萩原
皆で話し合って決めた卒園制作「ロボットカミィ」のぬいぐるみ作りをする。クリスマス制作で編み物をした経験もあり、紙以外のものを使った制作遊びに興味をもっている。保育者が穴を開けた部分に糸を通していき、縫い合わせていく。部品を合わせて、少しずつカミィの形になっていくと「こうなっていくのか」と見通しがつき、完成した形をイメージして喜んでいる。紙芝居のカミィを思い出し「お腹は〇〇色にしよう」「時計みたいな部品もつけたいね」と考えて友達と話し合う姿もある。3歳の時に共同制作で大きなカミィを作り、おたのしみ会の表現遊びでもカミィを題材にして取り組む。5歳児になってからも想いがあり、全員一致の意見でカミィのぬいぐるみを作ることに決まる。工作というより、手芸の要素が強いもので、新鮮味を感じて楽しんでいる。少しずつ、交代で進めていくことで友達と気持ちを共有することができている。完成させて、皆で達成感を味わえるよう、活動を進めていく。
3月 24日 (木) 晴れ 萩原
洋光台第三小学校に皆でつくった「おにいさん・おねえさん よろしくね」の手紙を届けに行く。小学校に入るまではうきうきとした表情をしているが、校長を前にすると、緊張したような表情を見せる児もいる。後、校舎周りだけではあったが、見学をする。校庭の日時計やメダカの泳ぐ池を観察したり、校庭でかけっこをしたりする。また、大掃除をしている小学生の様子に興味をもって見ている児もいる。これまで、「ランドセルを買ってもらった」「学校に持っていく道具を準備した」など、就学に期待や喜びを感じている児が多かったが、3月に入り卒園を実感していくと同時に就学への不安を感じる児が増えている。そんな不安定な中、実際に小学校に訪問し、様子を知ったり教諭や在校生と挨拶を交わしたり、実際の活動の様子を見ることができたことは良かったと思う。31日で保育園生活を終えると、翌日から小学校のキッズなどを利用する児が多い。大きく環境が変化する時期なので、情緒の安定を図っていけるようにする。
3月 31日 (木) 晴れ 萩原
円海山への散歩に出掛ける。昨日は、「もっと歩きたい」という名残惜しさを感じながら引き返すことになったので、早めに出発する。2日連続の長距離散歩で疲れが見える児もいるが、「今日はどのコースを行こうか」と期待を膨らませている。一心堂広場で休憩をとった後、地図を見ながらコースを決める。今回はおおやと広場やうばのふところ広場を経由する1時間弱のコースで、川や橋がありこれまでに読んだ絵本とイメージと併せながら楽しんでいる。また、時には樹の根やぬかるみで転ぶこともあったが、何度でも立ち上がり、最後まで歩ききることができる。保育園最終日ということで、最後に子ども自身が達成感や充実感を十分に味わえる活動を考える。中には長距離を歩くことに不安を感じる児もいたが、友達と励まし合いながら転んでも自力で立ち上がり、歩こうとする姿に大きな成長を感じる。豊かな自然に触れることも長距離を歩くことも少ない子どもたちにとっては、大きな挑戦だったとも思う。今回得た達成感や充実感をこれからの糧にしてほしいと願う。…
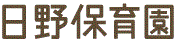

 5歳ひまわり組保育日誌バックナンバー
5歳ひまわり組保育日誌バックナンバー