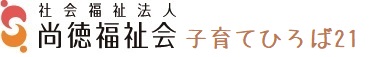常勤職をやる事が大事ではもちろんないんだけど、そういう事一つとっても要するに運良く体が丈夫なら、なんなく両立することもできますが、やっぱり大変は大変ですよね。そうすると、子どもを育てると言う事と生き生きと仕事が出来るということとそれがどうやって両立できるか、形として8時から6時まで預けて、勤務時間とつじつまが合えばいいというものでもない。もちろん親が元気いっぱいでも子どもがちゃんと育たないと困る訳ですから、その裏返しとしては子ども成長にとってちゃんとした条件がどう整えるか、その両方が問題なんです。
今少しずつ保育所に預ける率が増えてきてますし、結婚年齢が非常に遅くなってきてる訳ですけど、結婚しても共働きの率が上がってきてますが、しかし必ずしも全部が全部共働きでいきたいと思ってる訳ではないというか、日本は先進諸国の中で共働きの希望率はあまり高くない。5割ぐらいはいると思いますけど。どうしてかって言うと、あんなに大変な思いをしてまで両立させたいとは思わない、ということが非常に多い訳です。その大変さというのは先ほどから言ってるように、非常に現実的に負担がある、ぎりぎりでやってるとか、通勤時間が長いとかいうこともあるし、育児だけではなくて家事負担も女性側に非常に重いというような事もある。
これからの保育というのは形として、時間として育児と家事と働く事が両立するとか言うだけではなくて、或いは幼稚園で専業主婦、専業母親だったとしても同じで、大事な事は、子どもの健全な成長と言う事と親が生き甲斐を持って生きられると言う事の両方、親の生き甲斐は子育てによる生き甲斐もあるわけですけど。だけどもう一つ子育ての生き甲斐だけではやれないということです。数年間はやれるかもしれないけど10年間は保たない、もっと他の事もしたいそういう親の気持ちをかなえる事と、子どもが育つと言う事と最近の言い方で言えば親が育つということとその両方が必要なんだろうと思います。
その点については共働きであろうと専業主婦、専業母親で、幼稚園に子どもをやっていようと同じ事だと思います。つまり幼稚園に子どもをやってる場合には母親には自由な時間が多い訳ですが、しかし、多い自由な時間はもっぱら子育てと家事に使っている訳です。それで十分楽しみ生き生きやってる人は多いですが、先ほど言ったようにそれだけでは物足りない人たちも結構いる。フルタイムで働きたいとは限らないけれども何か部分的にしでもいいからやりがいのある仕事をしたいボランティア活動したい勉強したいと思う人もいるし、或いは今子どもが小さいうちは子育てに専念したけれど、どこかでまた社会に復帰して社会のかなで活動したいと思う人もいる訳ですよね。そういうことを可能にしていく社会にしなくてはいけない訳です。大きな事はもちろん国、行政、自治体がやる事ですけれどももっと個別で小さいレベルで具体的に自分の所に自分の保育園にきている親と子、幼稚園にきている親と子にたいして、何が出来るかいうことを考えていく必要があると思います。
そういたしますと、やるべき課題というのは一つは子どもが園にきてる訳なのでその園の保育というものをしっかりしたものにするということですね。それは当たり前なんですけどね。もう一つは子どもは園にいる時間、それが幼稚園なら4時間、保育園なら10時間、12時間ですけれども、以外に親によって育てれられているわけで、子どもが家庭に戻り、地域に戻ったときの子育てというものをよりよいものにしていくそういう働きかけがありますよね。これが子育て支援と最近言う訳ですが、それを良くしていく働きかけというものがあっていいわけです。三番目は親自身ですよね、子育て支援というときに親自身の問題も入れる事もありますが。親が育つこと親として育つと言わなくても例えば30歳の女性として35歳の男性としていろいろやりたいことがある、それをどう支援するかということです。これは男性で特にサラリーマンであれば逆に家に早く帰れるようにするとか、土、日ちゃんと休めるようにするとか、育児休暇を一年とは言わなくても部分的に出すとかなんとかというのは一つあります。
今日はあまり父親の話をする気はないんですけども、それは当然ながら非常に大事な事なんですね。父親が子どもに関わる時間というのはこの10年間でどちらかと言えば増えてきています。一番大きいのは土曜休みが増えたんですね。仕事の種類や会社にもよるでしょうけど、90年代に土曜日完全に休む会社が非常に増えました。この4月から学校の先生たちも土曜日休みになりました。やっぱり土、日休みになりますと、たとえたまに仕事が入ったとしても子どもの接触時間が増える訳です。普段は忙しくても土、日は家にいる訳ですから、それからもう一つ結構大事なのは、通勤時間なんです。地方だとあまり感じないと思いますけど、首都圏のあたり通勤時間長いですから、場合によると2時間なんてざらなんですけど、当たり前ですけど家にいる時間短くなっちゃいますから、やっぱり接触時間減りますよね。子どもが寝る時間がどんどん遅くなってきています。これは日本社会全体が夜更かし型に変わったからですけど、特に90年代ですね。三歳未満の子どもですね。だいたい保育園とか幼稚園とか朝は決まっていますし、家庭にいる幼稚園に来る前の子の就眠時間が非常に遅くなってきています。例えば夜11時、12時が平気です、って朝寝坊してるだけですけど。それはどうしてかというと親に合わせているからです。お父さん10時頃に帰って子どもと遊ぶというような暮らしをやってる、少なくとも首都圏では。
話を戻しますが、父親が育児、家事に関われる時間をどうやって増やすかという課題はこっちにあるわけですが、それはちょっと置いといて、母親の問題で言えば、母親自身の子育てをどうやって助けるかと言う事と、もう一つは母親が30歳、40歳の女性として生きてる訳で、仕事を持っていたり持っていなかったり、或いは将来仕事をしたいと思ったり、趣味をしたいと思っていたりするわけで、それをどう支えるかということも大事な事になる。それも実は幼稚園、保育所の仕事の一つに多少なってきたということですよね。
例えば一時預かりとか言うような事でも、保育園、幼稚園でそういうチャンスを作るようになってきたとか、或いはこの辺はあまりベビーシッターは盛んではないかもしれませんが、ベビーシッターとかを使いながら、或いは一時預かりなどをしながら、趣味とか、学習活動をしていくとかいうことが増えてきている訳です。
ということでですね今子育て支援という問題と、保育そのものという両方を、保育所でも幼稚園でもやりましょうと変わってきた。このことは10年ぐらい前から言われてきてると思いますけれども、両方が大事だと言う事がやっとここ数年現場の先生方に伝わったんじゃないかという感じがしています。
それまではやっぱり子どもを保育する事は大事だ、それはそうですけど、それが仕事ですからね、子育て支援など余計な事だなという感覚はあったと思うんです。保護者に関わるとか、子育て相談とかそういうのは自分の時間が空いたらするけどもただでさえ忙しいんだからそれは他の人がやってくれとか、クラスをもっている保育士は一生懸命保育して保護者との関わりとか子育ては園長先生に任せようとか、そういう感覚が強かったと思いますけども、そうじゃなくて、子育て支援というのと、保育というのが両方が同じくらい大事なんだというふうにだんだん変わってきた。
じゃー具体的にそれをどうやっていくかということなんです。保育自体の中は今動いているんですけど、それは後でお話しするとして、子育て支援のほうを先に話すとして、その背景として、今の親にとって特に初めての子どもを育てるということがなかなか大変なんだと言う事を理解していく必要があるわけです。結局今の親になる人たち例えば、20幾つとか30ぐらいの人が子どもを育てるということを見聞きしていない訳です。小さい子どもに接する事がそもそも少ないかゼロかもしれない、これも少子化と言う事が背景にあるわけです。身の回りに小さい子どもがいない、最近は中学生、高校生が幼稚園、保育園に行って子ども接するとというのが家庭科とか総合的学習などでやり始めておりますけれども、それまではあまりなかったです。近所に子どももいないと言う中で初めて赤ちゃんを産んで、育てる訳ですけれども、妊娠中に母親学級その他がありまして赤ちゃんはこういうもんだよとビデオ見せたり人形触ったり、先生のお話や、看護士さんのお話を聞いたりいろいろするわけなんですけど、最近はテレビでも沢山映像を流してる訳ですけど、でもそうやっぱりなかなか難しいこともあります。
赤ちゃんには個性がありますから、個性というか性格の違いみたいなのがあるわけです。テレビの番組では子どもをトントンっとしたり、なにかリズムのあるものを聞かせるとすぐに寝てしまう事になってますけど、実際にはそうもいかないので、なかなか寝ない子は寝ないですよね。子どもは保育園にずーといると神経が太くなるんだろうと思いますけど、平気でね、さっきも見せていただきながらわれわれが無神経におしゃべりをしていても平気で子供は寝てますけども、家庭で育ってる場合にやっぱり神経質な子は神経質ですから、ちょっと声が聞こえたり自動車の音がするだけで目覚める子は目覚めちゃいますね。夜泣きするとか、夜泣きしてお母さんが抱っこしてもなかなか寝ないとか、私は女子大で教えてますから、時々卒業生と会ったりして話しを聞いたりしますけど、例えばうちの子は、夜中に起きちゃうと横にすると寝てくれないからずーっと抱っこして寝かしたとか、夜中に自動車に乗せて一周しないと駄目だとか、変な癖をつけちゃったというのもありますけどもやっぱりそう言う場合もありますよね。
そういうのは恐らくたまたま親が甘えさせすぎたと言うようなことももちろんありますけど、子どもの性格と言いますか気質みたいなもんで寝つきが悪い子は悪いです。これは因みに大人になって寝つきのいい人もいるしそうでない人もいますよね、大人で寝つきの悪い人というのは大体子どものころから寝つきが悪いものでありまして、寝つきの良い人は子どものころから大体寝つき良いんですよ。大人になって瞬間的に寝る人っていますよね、みんなで旅行したりすると分かりますけど、枕についた瞬間に寝てる人っているんだけれどそうじゃなくて、30分とか1時間とかかかる、寝る前に儀式みたいにね、本読むとか音楽聞くとか何かしないと眠れないとかね。枕替わると眠れない人とか多いですよね。そう言う人は多分、わかりませんけど。赤ちゃんのときにもそういう傾向があったとおもいます。ですから夜泣きするとか、抱き癖つくというのは子どもの個性だと思いますけど、ともかくそういうことで苦労する親はたくさんいますよね。
そうでないにしたっていろんなことがありますよね。例えば最近良く1.2歳の家で育てる場合ですけど1,2歳で良く育児相談で出てくるのは、昔からそうですけど、食が細いというのと、オムツが取れないというとがよくあるわけですけどね。あるいはご飯を食べさせている途中で遊んじゃうとか、いろいろあるわけです。食が細いと言うときに大体先生の回答は、細くたって死にはしませんとは書いてませんけど、はっきり言えばそういうことですよね。その子なりに食べているんだから気にしなくてもいいよと、栄養は取れるものですということなんですけど、それは本当だと思いますけど、親としてはやっぱり心配、どうもうちの子は体が小さいし風邪引きやすいしやっぱり栄養足りないんじゃないかって心配になりますよね。
オムツ取れるのも保育園なんかだどやっぱり保育士の先生達は上手だから上手く取ってくれていい訳ですけど、家庭にいるとこれがなかなか難しいです。最近幼稚園も3歳児からの保育が増えたわけですけど、3歳でオムツ取れてない子というのはたまにいるんですよね。幼稚園の先生はそういうのになれていなくて非常に困るようですけども、例えば幼稚園って普通シャワーないでしょ、お湯がでないんですよね、おしり汚れたときに綺麗にする事一つとっても面倒くさいんですよね。そういう条件から始まってオムツの取り方もお母さんなら別だけどなかなか慣れてませんから面倒くさいんですけど、それは別としても30人ぐらいいると一人オムツのある子がいたりするわけですけど、遅い子は遅い、紙おむつが出てきてから随分遅くなりましたからね。だけど早い子は早いんですよ。なぜかね。満1歳ぐらいで取れちゃう子もいなくもない。平均は2歳前後でしょうけどそうすると公園かなんかで話をしてるうちに、うちの子は1歳半で取れたんだよ、とか言うとなんか早く取れたほうが偉そうですからね、「うちの子は満2歳過ぎていてもうすぐ3歳なのに取れないな」とか悩んだりする。悩む方が良いか、悩まないほうがいいかそれも難しくて、満3歳になってオムツ取れてなくて悩まないお母さんも困るんですけどね。極端な話満4歳ぐらいになってもオムツ取れなくても平気なお母さんもいるのも驚きますけど、そういう人もいますが、悩まなさ過ぎも困るんですけど、悩み過ぎも困るとわけです。
ちょっとした事というのは大勢の子どもがいれば、遅い子も早い子もいるなと思うし、おばあちゃんとかいろいろいると「あんたのお父さんも遅かったのよ」なんとか、かんとか「すぐおもらししてね。」という話になってあーそーかなと思える訳でなんとなく落ち着いてきますけど、そうでないとなかなかわからない。
或いは言葉が遅いにしてもそうですよね。やっぱり何十人に一人か分かりませんけど、言葉が遅い場合に本当の障害を持っていることもあるわけですよね。そうかもしれないな、いやでも違うんじゃないかと思っているうちに2歳半ぐらいになったら言葉がだーっとでて、急に普通になる事もあるし、そうでないこともあるわけですよね。
私の知っているある子ども、やはり幼稚園だった子ども、もう小学校になってますけど。は最終的にはいわゆる最近良く出てくるADHDという多動の子どもという診断が下されましたけれど、幼稚園の時に見て多動だなと感じて、そういうことを先生達にも言ったんですけど、いろいろあったなかで親御さんと私は面談したんですけどね、子どもの様子を伝えるとか話すために、お母さんが言ってたのは、上の子の時にはそういうもんかなぁと思っていたんだけど、下の子が産まれたと上の子が4歳下の子が1歳半ぐらいかな?なったときに「ああ!やっぱり上の子変だ。」と初めてそこで分かったと言っていました。つまり二人並ぶと下の子は年齢よりいいぐらいに明るく元気で、上の子は言葉が遅くてもたもたして、また多動でと言う子で全然違う訳ですよね。ということで、幼稚園の先生が心配だなんだと言っていたことがなかなか納得してもらえなかったのが、問題かもしれないと言う事で医者にも行ってくれた訳です。だから本当に障害もありますので親も心配する訳ですよね。
それからそういう心配だけではなくて、子どもにどう接するか自体がよくわからないということがあります。実際子どもへの接し方が分からないというのがあります。まあ育児は半ば本能だから子どもと接していれば自然に覚えるというのは半分ぐらいは本当なんですけど、全部が本能じゃないです。やっぱり覚えていくものです。子どもがニッコリすれば親もニッコリするもんなんですけどね、親と言わなくたって私がそこを歩いていて子どもが寄ってきて引っ張るから「なあに?」って聞けばついニッコリしますよね。こっちがニッコリすれば子どももニッコリしてくれて、自然にやりとりが成り立つものなんですけど、ただ7,8割の親はそれでうまくいくものですけれど全員が全員そう上手く滑らかなやりとりのサイクルにうまく入れるとは限らない訳です。
それは親の持っている問題がありますよね。例えば小さい頃からいろいろあってなかなか可愛がるという経験、可愛がられると言う経験をあまりしてなくてそうすると、可愛がるということが良く分からないという人もたまにいます。そういうことはなくて普通なんだけど、例えば夫婦仲が悪くなっていつもイライラしていてとなればどうしたって子どもに当たったり、子どもが泣いていても面倒くさくなってしまいますよね。これもわりと多いとおもいます。そう多くはないけど時々はあります。
出産後の鬱というのは産後1か月からせいぜい6か月ぐらいまで、だいたい2,3,4か月ぐらいのときですけど、落ち込むというのは研究によってパーセントは10%ぐらいという人もいるし、30%ぐらいというひともいるけど、結構多い訳ですけど。それが少し長く続く場合もあります。そうすると鬱っぽい状態というのは応対がない訳ですよね、面倒くさいというのかな?子どもが少々泣いていてもすぐに行けないとか、自分が憂鬱ですから相手が微笑んでも、微笑み返す事ができないわけです。そうすると子どもの方だって微笑まなくなるし、声を出さなくなっちゃいます。
そういった親の問題もある訳ですけど、深刻なケースではなくてもどうもこうやり方が上手くわからない、子どもをどう躾て良いかわからないとか、子どもをどう抱っこしていいかわからないということもある訳ですよね。そうするとこういうのをなんとかしていく必要があります。
じゃ具体的に子育て支援というもの、そういう子育てについていろいろ悩みを抱えていたりどうしていいかわからない人たちをどうしたらいいか。もちろん障害児かどうか心配しているなら見てあげて伝えてあげて、どうしたらいいかという具体的なことをやれば良い訳ですが、子どもをどう育てて良いかわらないというのはなかなか難しいので、「やーそれは可愛がるんだよ」とか「ニッコリしてごらん」って言われて出来るくらいなら最初からやってるんで、それができないわけです。やっぱり具体的に見本を見ていく必要がある訳です。
じゃー見本はどこで見せたらいいの?親をここに呼んでここで見本を見せてと言ってもしょうがないです。ビデオ見せてもあまり変わりませんから。例えば親の小グループにして親と子がそろいながら何人かで一緒に遊ぶというような経験をするなかで、こんな風にするもんなんだというのがだんだん分かってきて、つまり他の親が子どもを可愛がる様子を眺めながら、段々段々段々そうだなぁと分かっていくとか、或いは自分の子どもを他の人が世話してるときに他の人に対してすごくいい顔をする、あっうちの子ってこんなにかわいいんだと初めて分かるとか、そういうこともある訳ですよね。そういう事を保健所とか公民館とか場合によっては病院とかグループでやったりするわけです。極端な人を集めただけじゃなくて、例えば保育所でも或いは最近は幼稚園でも3歳未満の子どもの母子を集めたクラスやグループを作ったりしますが保育所はもちろんいろんな年齢の子どもと親が来る訳ですけど、そういうなかで親子と子が一緒になる機会を増やしていく、或いは親が保育に見学するとか参観するとか最近は更に親が保育に参加する保育の手伝いをする自分の子どもとは限らなくてですね、クラスの面倒見るとか他の子どもの面倒見る機会を入れていくということもやり始めているわけですが、そういう経験を通しながら親が子どもを育てる事の細かい技術と言うよりは親が自信を持って子どもを育てられるとか、子どもを育てる事は楽しいんだなと思えるようにしていくとか、迷ったときにいつでも聞ける相手を作っておくんです。
悩む人って言う人は例えば地方から都会に出てきて孤立しているとか、もともと産まれ育った土地とは離れていて自分の親とは今連絡が付かないとかそういうことが多いですよね。そうすると自分の親にも相談できない、近所の人ともなかなか話せない、性格的にもなかなか堅くて公園に行ってすんなり話す事が出来ないような人は孤立しやすい訳で、相談とか大げさな事言わなくても、ちょっとした悩みを交換してるうちになんとなくあーそうかなと思えるようになる訳だからそういう機会を作るようにしていくそういう事が子育て支援ということになっていく訳です。
さてそれに対して保育自体の話も加えたいので、ちょっと話しておこうと思うんですけど、幼稚園、保育園の保育ですけど、最低基準と最高基準と言う言い方をしているんですが、最高基準というのはちょっとあんまりいい言い方ではないんですが最低基準というのは何かこれは例えば国や自治体の基準なんですね、例えば認可保育所なり幼稚園の基準というのがありますよね。これは最低基準なんです。つまりこれを満たしていないとまずいよと言ってる訳です。無認可って言ってもいろいろなレベルがあるので、本当にひどい所もあるし認可に近いレベルなりこうそれなりの基準を持っている所もあるんですけどもともかく最低基準としたら、保育室はこれくらいの広さあるとか、そこに遊具がいるんだとか0歳児クラスなら先生1人に対して子どもは3人までであるとかなんとかとこう定員だとか決まってますよね。それから先生の専門家としてのレベルとして資格を持っていなくてはいけないだとか、資格を持つためには日本の場合には今専門学校、短大、2年以上の学校をでるか、或いは試験で取んなきゃなんないですね。そういうような事は最低基準です。
その最低基準というのはそれより下回ると問題が出るというわけです。それはまずいぞと言う事なんだだからまず必要な事は最低基準をクリアすることなんです。ここにいらっしゃる方に言っても仕方がないんですけども、世の中には最低基準を割っている所が沢山ありますので、念のために言いますけどその無認可といってもピンからキリまであるので、ピンの良い方はちゃんとしてますけど、キリの方もなくもない、中には新聞で出るように赤ちゃんを虐待したり、殺したのか事故か分からないけれど死んじゃう場合もある訳で、困る訳です。本当にこう特に東京周辺には駅前保育所というのが沢山ありますけども駅前保育所もかなりしっかりして大体、庭はないけれど、大体普通の保育所なみの施設を持っている所もあるんですけど、そうではなくてまさにマンションの一室の中に何人かいるだけというところもあるみたいです。だから本当にピンからキリまであります。昨年度法律が通って無認可であっても子供を預かっている場合には行政に届け出て、行政の方が立ち入り検査をするということがやっと明確に決まりまして多少改善されるでしょうけど、しかし無認可というのはようするに基準がない、無いというと、もう少し言うと補助金が多少出る事によって自治体ごとに基準が少しあるんですけど。そういうのいらないよって言えばないんです。ですから悪い方の歯止めって子どもの生命に関わる所は行政はチェックしますけど、一応こうミルクも与えられているし殴られてもいないしというレベル以上の事は無認可については行政はチェックしない。しかしまあ子どもはミルク与えられて殴られなければ育つのか?というと違う訳ですから、でもそういうところがあるのだから、まず直さなくてはいけない。それは悲しい現実だけでありますね。
それに対してしかし大部分の認可された保育所及び幼稚園はそれはクリアされてるから認可されてる訳だから問題はその先にあります。実は子どもを育てる、教育するとか、育てるというのは最低であればいいわけじゃない、飢え死にしなけりゃ人間いいってことじゃないです。やっぱり文化を持った人として育たなくてはいけない、人を愛する人として育てなくちゃいけないわけで、そうすると高い水準を目指すと言う事になります。
じゃ高い水準を目指すのはどうしたら良いか、高い水準と言ったって、どんどんどんどん要求は上がっていきますから、そういう事で言えばどの幼稚園だって保育園だって100点のところはないです。必ず改善の余地はある。この保育園はすばらしい所ですけど、ここだって多分改善の余地は沢山あります。特に出来たばかりですもんね、庭なんかはまだまだこれから整備しなくてはいけないと思いますけども、そうじゃなくて有名な保育園だろうと幼稚園だろうと改善の余地はいろいろあるわけです。
そのときにじゃー、やっぱりどういうことまでいけばいいのかという、理想とはいわなくてもいいんですけども、このへんにいったほうがいいんじゃないかということを持っていないとなかなか改善できません。だからある程度世の中理想論というのは必要です。ああいう所にいきたいなと思わないと、現状が見えない、つまり保育の恐ろしい所と言うかいい所でもあるんですけど、とにかく子どもを預かっている訳ですよね。親は朝送りにきて、夕方迎えにきますよね。その間親は見てないわけです。見てないからと言って悪い事するわけじゃないけどね。でも不安だって言うのでインターネットで映像で送ろうというシステムがあるけどあんまりあれは日本で普及するとは思わないんですけど、だから悪いことしてる訳じゃないけどまあより良くなってるかということですね。その時に何となく子ども預かってるし、元気良くやってるし子どももニコニコしてるし、よく食べたり飲んだりしてるしいいじゃないって言う訳にはいかない。それは100点満点、保育に点数を付けるものではないけれどただ、大学の点数で言えば60点が優良可、大学の成績で60点ならいいかとそういう問題ではないんですね。やっぱり80点、90点目指すべきでしょ!
1-4へ続く…