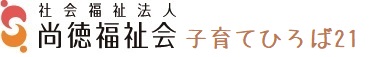第3回講演会 ひとりでがんばらないで 3-10
ひとりでがんばらないで
この一番最初にお渡しした紙のいよいよこの「ひとりでがんばらないで」っていう所に入っていきたいと思います。
今までの話を整理して聴いていただいたら分かると思うんですけども、頑張ってすごく疲れている人に私達がかける言葉にどんなのがあるでしょうか。ものす ごく一所懸命です。自分の力を信じて外からの力を跳ね返しながら、それから自分の気持ちを表現しながら、いっていかれてる、その方達に頑張らなくていい よって言うのは違うなって思ってるんです。頑張っておられるんですから、ものすごく。頑張らなくていいよって、ものすごく失礼だと思うんです。それで、頑 張らなくていいよって言わない代わりに、「ひとりでがんばらないで」って伝えたいわけです。そしてその前に無理をしないでね、自分の体を大事にしてね。そ のことを伝えていきたいなと思います。今うなずいてくださってた方がたくさんいらしたんですけど、ご自分のことに置き換えて考えられるととてもよく分かり ます。頑張る為には安心して過ごせる場所が必要です。子どもさんにとって頑張るのに安心していられる場所っていうのは、お家の方の側です。一番最初に0歳 の時に大好きになった、安心していられる場所だなーと思った、お家の方の所が子どもさん達が外に出ていく一番の港になるんだってこと、よく言われますよ ね。その港であるお家の方達が疲れていると子どもさん達が疲れて港に戻ってきたり、外で怖い思いしたり、暗闇が怖かったりいろんな経験をしながらお家に 戻ってきたときに、港の中が外の海よりももっと大荒れだったら、子どもさん達帰ってくる場所なくなってしまいます。なので、みなさんの港が穏やかでいられ るように、先ほどから私が話してきたこと、ご自分のご家庭に当てはめたりご自分の気持ちの中に当てはめて、一度誰かと話をしてみていただけたらいいなと 思ってます。こういう言い方をされる先生があります。心の安全基地っていうんだそうです。子どもさん達が帰る心の安全基地であるお家の方の心の中の安全基 地が出来ているということが必要だそうです。なので、ここにいらしているみなさん一人ひとりの中に、自分が大事だなって気持ち、自分は好きだなって気持ち と、それから、私のことをちゃんと見ててくれている人がいる、私のことをちゃんと分かってくれてる人がいる、そういう人を作って置かれて、それがあるから こそ子ども達がお家に帰ってきたときにお父さんやお母さんやお家の方の元が安心して戻ってこられる場所になってくるといいですよね。
こういうお話しをしていくと、傷つかれる方が出てきます。ちょっとここから嫌な思いをする方がおられるかもしれないですけど、ご自身が小さい頃どういう 環境の中で育ったかっていうことを思ってしまわれる方が、あると思います。自分自身は安心した中で暮らせてきたのか、落ち着いた気持ちでいれたのか。この 私にはこの子ども達を見てていいのかって気持ちがあると思います。ものすごく不安だと思うんですけれど、それは元に戻って取り返さなくてもいいものではな いかと。みなさんが今この年になっておられて0歳や1歳になって取り戻さなくてもいい。小さい頃に辛い思いをされてきた方の中には、ご自分の子どもさんに 実は手が出てしまう人もおられると思います。ご自分自身を痛めつけてしまう人も中にはおられるらしいです。しかし、そういうことをしないで暮らしていける 方もたくさんいらっしゃいます。そう出来る分かれ目になるところっていうんでしょうかね、自分の心の中に安心だなって気持ちが持てたか持てなかったかは大 人になってからの出会いの中にも、実は出来ている、あるんだそうです。なので、ご自分が小さい頃からこういう目に遭ってたから自分は子どもが見られない じゃなくって、だから、私は今自分の心が落ち着いて安心していられるような人、あるいは、物をご自分の心を落ち着かせるものを持っていようと、思う気持 ち。それがね、とても大事なんだそうです。自分の気持ちを表現するのに自分の気持ちの中にあるもの全部語ってしまうことはないわけです。辛かった苦しかっ た、こんな私は体験をした、そんなの吹き出すように話したらね、ぼろぼろになってしまいますのでね、それはお話しなさることはないと思います。辛かった記 憶はご自分の中に止めといて、おっしゃらないこともそれも一つの元気、自分ていうものを大事にする方法だという方もあります。どこかで辛い思いをしてこら れた方がもしあって、こういう話を聞いたときに、自分はどんな中で育ってしまったかって思ったときには、そう思わないでくださいね、ってことを是非伝えた いと思います。今、側にいるお友達や、ご家族の中に私のことを好きだと言ってくれる人がいたり、大事だと思ってくれる人がいる。そういう人を是非見つけて くださって、ご自分を傷つけない、それから子どもさんに対して、ご自分の満たされなかった思いをぶつけないですむようにしていっていただけたらなというの が、私が一番今日お話ししたかった内容です。
今日この私の話の中で、一度だけ虐待という言葉を使いました。ただ私は普段この言葉をあまり口にしません。言いません。これはね、子どもさんに対して、 手を挙げたり言葉で傷つけてしまう方達がひどい人だと思っていないからです。その方達は、あるいはそういうご家族の方達は長い間長い間ご自分達が苦しんで こられた、ご自分でも気がつかないけど、なんか抱えてこられた、そういうものにみんなが気がついていかないといけないと思うからです。いろいろな所に実 は、相談室ってあります。福祉事務所の中にこの相談室があるのとってもいいと思うんです。先ほどから言いました、エンパワメントって考え方は実は障害者福 祉のところでよく言われるんです。ご自分が例えば足が不自由で歩けない、と歩けないことをその人の力として評価するのではなくて、歩けないけどこれが出来 るという出来る方の力をとても大切に見ていこうというのが福祉の世界の考え方です。これがご家族の辛い思いを受けとめていく相談室の役割だろうと思いま す。実際にみなさんがよくお耳にされる、児童相談所ってありますよね、児童相談所ってそういう事をするお家のことを、する人をしかる場所みたいに思ってお られる方もあるかもしれませんけど、実はそうではないです。児童相談所という所は、児童福祉の最先端の機関です。子どもさんを育てておられるお家の方を 守ってくれる、助けてくれる場所だと、思っていただいたらいいと思います。福祉というのは、人の中にあるありのままにいていい自分、さっき言ったエンパワ …