5歳ひまわり組2023年度12月のまとめ
健康
鼻水や咳などの風邪の症状が多く見られるようになる。水分を摂る回数が減ってきているので、適宜声を掛け、風邪予防を心掛けると共に一人一人の体調の変化に気を付けていく。気温が低くなるが体を動かすと温かくなることに気づいて、ドッヂボール、氷おになどの運動遊びをする。活動の前に準備運動をすることで、体が温まり怪我の予防になることを伝えていく。のびのびと体を動かす心地よさを感じられるような活動を積極的に取り入れていく。
人間関係
友達同士で話し合い、遊びを進めていくことが多くなり、自分の気持ちを主張するだけでなく、相手の気持ちを汲み取ろうとする姿が見られるようになる。トラブルで友達が困っていると寄り添ってあげたり、仲介をしたりする。お楽しみ会の活動を通して友達との関わりがより一層深まる。友達と相談をし、気持ちの折り合いをつけながら遊びを展開できるように話し合う場を作り、見守っていく。
環境
年末に保育室の大掃除に取り組む。普段気付かない汚れに気付き、意欲的に掃除を進める姿がある。みんなで協力して綺麗にする心地よさを共感することができる。冬の自然現象に気づいたり、発見したりして四季の移りを感じていけるよう散歩に出掛けたりする機会を作っていく。
言葉
文字の多い本を読んだり、なぞなぞやしりとりなどの言葉遊びをしたりしている。文字への興味が広がっているので、様々な種類の本を準備したり、手紙のやり取りなどができるように必要なものを用意したりして、一人一人の興味や関心に合わせて援助していく。
表現
おたのしみ会活動の合奏では、自分が鳴らす音やリズムのタイミングを覚え、友達と一緒に演奏することを楽しむ。合唱では手話にも挑戦し、歌詞に合わせた手話表現を覚える。劇では、登場人物の気持ちをイメージしながら台詞の言い方や手振りを考える。様々な体験を通して、イメージしたことを形にする楽しさを味わえるように環境を整えていく。…
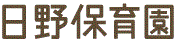

 5歳ひまわり組月のまとめバックナンバー
5歳ひまわり組月のまとめバックナンバー