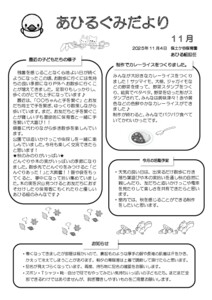1歳あひる組2025年度11月のクラスだより
おたよりが読み込まれるまで時間がかかる場合があります
8月5日(火) 天気:晴れ
朝おやつ後、ホールにて30分程過ごす。大型ブロックでつくったアスレチックやボール投げを行い活発に過ごしていた。その後、あひる組に戻るチームとうさぎ組に行くチームに分かれて過ごした。あひる組ではテントの中に入ったり、お絵描き、滑り台を楽しんだりしていた。うさぎ組に遊びに行った子たちは、ままごと遊びを中心に楽しみ、人形にご飯をあげるなどお世話を楽しんでいた。ホールや室内では大まかな遊びは設定したが、その中での細かい遊びは保育者はあまり仲入せずに見守った。すると、集中して遊び込んだり子ども同士で遊びを展開させたりする姿が見られて良かった。
8月13日(水) 天気:晴れ
今日は、うさぎ組と合同で水遊びを楽しむ。登園児12名で少人数ということもあり、アットホームな雰囲気で過ごせた。久しぶりの水遊びだったが、嬉しそうに満喫する。ジャグにフルーツを入れたり、うさぎ組と一緒に色水を作ったりして楽しんでいた。
年上の真似をしてコップに色水をいれて、色の混ざりを楽しんだ。蛇の玩具を気に入って嬉しそうにしっぽを持って揺らす子、タライの水を手でたたく子など自分なりの楽しいを見つける。異年齢の交流が自然に出来て年上の遊びに関心を向けていた。クラス関係なく保育者も子どもたちと関わる事ができて良かった。
8月18日(月) 天気:晴れ
お盆明けで人数も多くなり賑やかな一日だった。久しぶりの登園で、受け入れ時に泣く子も担任が抱っこをすると泣き止み、信頼関係が見られた。ホールで過ごした後は、ひよこ組と合同でどちらの部屋も行き来ができるようにした。ひよこ組では、音の出る玩具や玉転がし、あひる組の部屋には平均台やテント、マットの山などを出すと、子どもたちは気分によって遊び場所を変えて過ごしていた。廊下では、ボールを投げ合い友だちと関わる時間にもなった。今までは、夕方にひよこ組の玩具を貸してもらうことはあったが、全体で自由に遊ぶのは初だった。なんとなく年下ということが分かるのか、優しく一緒に遊ぶ姿もみられ良い時間となった。
8月20日(水) 天気:晴れ
朝の時間は、絵本や塗り絵などをして落ち着いて過ごしていた。おやつ後は、ホールへ行き、テラス前の階段でミニ滑り台や、保育者のピアノでリトミックを楽しむ。部屋では、ちょうちんの作り楽しむ。ビニールの中に絵の具と画用紙を入れての制作だったため、絵の具のプニプニとした感触を楽しむ子や手に絵の具がつかないのを不思議に思う子もいた。その後、クレヨンでお絵描きをした。塗り終わった頃に、保育者がその紙を色々な形に切って、可愛い形のはがきを作った。また、段ボールをポストに見立てると、お手紙屋さん(郵便ごっこ)に発展し楽しめた様子。子どもたちの動きに合わせて遊びが広がっていると感じた瞬間だった。
健康
咳、鼻水が出ていたが機嫌良く登園していた。8月中旬から発熱などの風邪が流行り、休む子もいた。夏季休暇の子で疲れが見られる子が多く、機嫌がいまひとつな時は、ゆったり過ごせるようにデイリーを早め身体を休めるようにした。登園時や活動前、活動中にもこまめな水分補給を行い、排泄状態も把握しながら、熱中症予防をしていく。汗をかいた時には、こまめに着替えをしたり、必要に応じてシャワーをしたりし、気持ち良く過ごせるようにした。手を洗う際、石鹸を付けすぐに水で流してしまう子もいるため、保育者も一緒に洗い、手を添えながら洗うようにしていく。
引き続き、子どもの体調変化に気を付けながら、より一層、熱中症に気を付けていく。
環境
暑い日が続き、室内で過ごすことが多かった。そのため、少しでも気分転換ができるように、0歳児や2歳児クラスと連携を取り色々なクラスを行き来できるようにした。また、スライム・氷・はるさめ・小麦粉粘土など様々な感触遊びを取り入れたり、運動遊びを取り入れたりすることで、どの子も飽きずに落ち着いて過ごせていた。まだ猛暑日が続くため、子どもの体調や表情を見ながら快適に過ごせる環境をつくり、他クラスと連携を取りながら、玩具の入れ替えなどをして、これからも遊び込めるような環境に工夫していく。
言葉
キャラクターなど、興味のあるものを言葉に出している。低月齢の子も自分の思いを伝えようと、喃語や片言の言葉、仕草等で伝えようとする姿が見られる。高月齢の子は、二語文ほどの言葉で話す姿が増え、友だちや保育者とやりとりを楽しんでいる様子が見られる。「これはなに?」「○○ちゃんはどこ?」など、保育者に質問する子もいて、様々なことに関心を持っている。丁寧にゆっくり話しかけることで、言葉のやりとりを楽しめるようにしていく。
自己主張が目立つ。イヤイヤをして自分の思いを発揮し、思い通りにいかない時は、泣いて訴えている。その都度、その子の気持ちに寄り添い思いを言葉で代弁することで、気持ちの切り替えができた様子。イヤイヤ時期を温かく受け止め見守っていく。
人間関係
様々な保育者と安心して関わる姿がある。また、クラスの友だちの名前を呼んだり、登園時に嬉しそうに駆け寄ったりする姿も多く見られる。友だちとの関わりが増えた分、トラブルも増えてきた。言葉がまだ上手く出ず、手が出ることもあるので、保育者が仲介しながら、友だちとの関わりを楽しめるようにしていく。
また、友だちと一緒に同じ玩具で遊んだり、物の貸し借りなどのやり取りを楽しんだりし、微笑ましい姿が増えた。
表現
感触遊びでは、はじめてのものに不安そうな子もいたが、保育者や友だちの姿をみてやってみようとする姿が見られた。保育者の言葉を真似して、“コネコネ”“ねばねば”など言葉で表現している。制作では、“あか”“あお”など、色の名前をいいながら、大きく手を動かして描いている。感触遊びや制作を通して、見立て遊びを楽しんでいた。
【幸せなら手をたたこう】など曲に合わせて体を楽しんでいる。
食育
暑さもあり、食欲が進まない日があった。スプーンですくって置くと手に持ち、口に運ぶ姿がある。自分でスプーンを使って食べようとする姿も見られる。“これは?”と食材に興味を示す姿があるので、“にんじんあったね”“お肉おいしいね”など、子どもたちと会話を楽しみながら食事をする。
保育者から励まされたり、褒められられたりすると、食べ物に興味がなかった子も意欲的に食べだす。また、その姿に影響をされ、「見ててね!」と他の子も意欲的に食べる姿が見られた。

 1歳あひる組
1歳あひる組