5歳らいおん組2017年度2月のまとめ
健康
○上旬にインフルエンザBが3名診断される。
○手洗いうがいの清潔面は自分たちで意識できるようになってきたが、袖をまくることを忘れてしまう児が数名見られた。その都度声を掛けることで少しずつ自分で気付けるようになっている。
人間関係
○先月に引き続き、友だちともめてしまっても自分たちで解決ができるようになっている。どうしても解決できない時でも、側で見ていた児が「それが嫌だったの?」「じゃあこうするのはどう?」と、提案したり話を聞く姿が見られた。
○「遊んでなかったけど手伝うよ」と自分が遊んでいなくても玩具の片付けを手伝う姿が全体的に増えてきた。
環境
○なかよしランドに期待が持てるよう、各グループで品物作りやシミュレーションをするなどして進めていった。
○卒園に向けてのアルバム作りでは、思い出ページ作成や手足の型を取り「遠足楽しかった~」「〇〇君の足大きくなった」などと、思い出をみんなで振り返りながら取り組んでいけた。
言葉
○相手に対して柔らかい言葉表現を使えるようになってきている。
○小さい子と積極的に関わり、お世話することや遊ぶことを喜び、優しく声を掛けたり、分かりやすい言葉を選んで使おうとする姿が見られた。
表現
○なかよしランドの2日間は、積極的に声を出してお客の呼び込みや接客を行なっていた。「今ならすぐにできますよ~」「あと○個でなくなりますよ」など、自分の経験を元にして呼び込む姿が印象的であった。
…
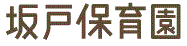

 5歳らいおん組月のまとめバックナンバー
5歳らいおん組月のまとめバックナンバー