5歳ひまわり組2021年度6月のまとめ
健康
歯科健診や内科健診を通して、自分の身体に興味をもつようになる。内科健診前に聴診器を使って心臓の音を聞いてみると、微かに聞こえる音にじっと耳を澄ませている。その後、図鑑やパズルを使ってさらに身体の仕組みについて考えてみる。健康な身体についての関心が高まってきているので、栄養や運動と繋げて捉えていけるようにする。
戸外遊びではゲーム遊びなどで意欲的に身体を動かして遊ぶ。適度に休息や水分を摂ったり汗をかいた後は着替えやシャワーをしたりして心地良く過ごせるようにする。
人間関係
遊びや生活の中で、困った場面で声を掛け合ったり助け合ったりする姿が多く見られるようになる。また、年下児の手伝いが増え、感謝されたり認められたりすることで年長児としての意識が育ってきている。さまざまな人と関わる中で、相手を思いやる気持ちを育んでいけるよう援助をしていく。
環境
昨年度から育ててきたカブトムシが成虫になる。「ちゃんと大人のカブトムシになったね」と友達と手を取り合って喜び、じっくりと観察している。図鑑と実物を見比べて角の大きさ形や脚の向きなどを細かく見ている。残念ながら翌日には死んでしまったものの、優しく撫でたり手を合わせたりしている。これから虫の多い時期となるが、命の儚さや大切さを感じることができるよう関わっていく。
言葉
文字や言葉への興味が高まり、しりとりや回文などの言葉遊びを友達や保育者と一緒に楽しむ姿が増えてきている。また、50音表を見ながら友達や家族に手紙を書いてみようとする児もいる。楽しみながら文字に触れていけるよう、遊びや活動のもち方を考えていく。
当番活動では、挨拶・日にちや天気の確認・出席確認を担当する。人前で話すことに緊張を感じている児もいるが、経験を重ねていくことで大きな声で話せるようになってきている。人前でも自信をもって話ができるよう援助していく。
表現
七夕飾りの制作では、折り紙や染め紙など伝統的な制作を取り入れる。折り紙では紙の質や大きさによって折りにくさを感じることがあるが、繰り返し折っていくことで指先の使い方が分かり、自分で考えて折ってみようとするようになる。地域の七夕用の飾りでは大きな作品を作り、満足感・達成感を味わっている。さらに制作活動を深めていけるよう、さまざまな制作方法を提供していき、今後協同制作にも繋げて行けるようにする。…
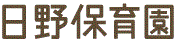

 5歳ひまわり組月のまとめバックナンバー
5歳ひまわり組月のまとめバックナンバー